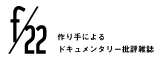『記憶の戦争』イギル・ボラ監督インタビュー
11月6日(土)よりポレポレ東中野で公開される『記憶の戦争』は、ベトナム戦争下で行われた韓国軍によるベトナム人虐殺事件の記憶を描いたドキュメンタリー映画。虐殺の生存者の話に耳を傾け続けるイギル・ボラ監督の姿勢がとても印象的だ。加害国の作り手として、被写体とどのように向き合い、葛藤したのか?イギル・ボラ監督に話を聞いた。

―まず映画を製作するにあたって監督としての思いを教えてください。
私は映画を製作し、文章を書いているアーティストです。また活動家でもあります。私は、この映画で取り上げた50年前のベトナム戦争だけでなく、今の時代にも起きている虐殺や国家暴力、難民の問題、そういった暴力をどのように記憶していったらいいのか?どうして繰り返されるのか?どのように先に進んだらいいのか?その答えを探してみたいという思いからこの映画を製作しはじめたんです。
―『記憶の戦争』は被写体となる人々との距離感、そして彼らの話を聞くことに徹した抑制されたトーンがとても印象的でした。イギル・ボラ監督のおじいさんがベトナムへ派兵されていたことを知ったことが、この映画を製作するきっかけだったと伺っています。今回、監督自身の視点を通して物語るというスタイルを、あえて採用しなかった理由を教えてください。
映画を作るにあたって、いろいろな選択肢がありますよね。私が主人公になって、私の視点でアプローチするという方法もあるでしょうし、この『記憶の戦争』のように少し距離を置いて視るというスタイルもあります。私はこれまで2本のドキュメンタリー『ロードスクーラー』(2008)『きらめく拍手の音』(2015)を制作しました。いずれも私の視点で物語る作品でした。今回の『記憶の戦争』は、もともとの出発点となったのが祖父の派兵ですが、今回はアーティストとして違うスタイルに挑戦したいと思ったのです。
―これは同じ作り手として感じることなのですが、監督の視点で物語る作品は登場人物を監督の物語の一部として利用しているかのような感覚がどうしても拭えない時があります。実はイギル・ボラ監督も、このようなスタイルを採用した背景にそのような後ろめたさもあったのではないかと推測しますが・・・
そうですね、似たような悩みは私も抱えていました。この映画では主な登場人物を3人に絞ったのですが、映画の中で誰を登場させるべきか本当に悩みました。この人の話もあるし、あの人の話もある。誰の話が大事なのか、私には断言できません。
ある時、「主人公の一人を韓国のベトナム戦争に参戦した元軍人にしたらどうか?」とアドバイスしてくれた方がいたんですね。でも私はその助言を受け入れませんでした。なぜなら、少なくとも韓国軍による虐殺の問題はまだ解決していないからです。ベトナムで今でも苦しんでいる方がいらっしゃるのに、バランスをとって韓国の苦しんでいる人を登場させるのは「本当にフェアになのだろうか?」。そして、「まだだ。その時期ではない」。まずはベトナムの人たちの話を聞くのが先だろうと。
例えば、この『記憶の戦争』が公開された後で私が再び同じテーマで撮るとしたら、参戦軍人に話を聞くといった、また違ったスタイルになるでしょう。でも、少なくともこの映画が完成した2018年の時点では、まだベトナムの人たちの声が韓国に届いていない状況だったので「聞く」という事に焦点をあてました。だからこのようなスタイルの映画になったとも言えます。



―今回の登場された3人の方とは、どのように関係性を築いたのでしょうか?
ベトナムには2015年から2019年にかけて、一年に一回。計五回訪問しました。一回の訪問で一か月くらい滞在しました。まず現地で知ったことは、ベトナムではカメラは違った意味があるんだということです。日本と韓国であれば、みんながカメラを持っていて、ユーチューブを見ていてカメラに慣れていますよね。でもベトナムとなると事情が違います。虐殺のあった村ですし、韓国の人がカメラを持って入るということ自体が暴力的なことになってしまうんです。
最初にベトナムに行った時は慰霊祭を取材しました。カメラも持って行っていたんですけど、出しませんでした。もちろん撮りたい欲求はありました。これを撮っておけばあとで使えると思いましたから。けれど、いきなりカメラを向けるのではなく、まず黙とうをしました。それからスタッフとも話をして、最初の取材はカメラを向けずに話だけを聞く方針に決めたんです。
―カメラを持つことが暴力的になると知った経緯を教えてください。
ベトナムに行くと、都市と虐殺を受けた村ではずいぶん雰囲気が違うんです。都市では韓国から来たというと「K-POPすごいですね、豊かですね」とか言われます。ですが、虐殺のあった村に行ったとき、私が韓国人という理由であいさつをしても受け入れてくれない経験をしました。とてもショックで、同時に罪悪感を覚えました。彼らは韓国人が前に座っているだけでも不愉快な思いをしたり、怖いと感じてしまうのです。そのような人たちの前で、いきなりカメラを出してしまったら・・・それはとても暴力的な行為になると感じました。
それにドキュメンタリーを作る場合、やはり関係性が大事です。相手との関係性を築くことで深い話を聞くことができますし、相手との距離感も縮まっていきます。相手が不愉快な思いをすると知った以上、カメラを出すのが正しいのか?と改めて考えました。そして、十分に親密な関係性を築き、より理解した上でカメラを向けた方がよいという風に考えたのです。
そもそも最初の関係性自体が暴力的ですよね。カメラを持った若い韓国人が何回もやってきて、お話を聞いて映画をつくる。でも相手は一回も韓国に行ったことがなくて、昔韓国人がやってきて村の人を殺された。一方で、韓国人である私たちはその理由を知らないで生きてきた。そもそもフェアな関係性ではないので、カメラを向ける事、それ自体が暴力的なのです。
この問題はすごく難しい問題だと思います。作り手の倫理観が大事になってきますし、映画が終わってからも相手との関係が続くので本当に難しいと思います。映画に登場するグエン・ラップさんがこう言いました。「自分たちは貧しい、だから韓国の人たちに助けてほしい」と。でも自分たちは何もできないんですよ。本来は、韓国政府が被害者を補償しないといけないんですけれど、まだそれがなされていない。私たちの方でなにか物資を援助することはできないですし、映画を作った後に後援とか支援ができないだろうか?とも考えました。でも、映画を作った後にお金を渡すこともできないですよね。村で被害を受けた方が他にもいらっしゃるので、特別な人だけにお金を渡してしまうことはできません。ですから、私は「この映画を作ったら何ができるんだろう・・・」と、とても悩みました。おそらく日本で活動されている作り手の皆さんも、同じような倫理観に対する悩みは常にもっているかと思います。
―そうですね、私たちも常に悩みながら制作しています。イギル・ボラ監督はドキュメンタリーにおける倫理観に関してとても自覚的であると感じますが、それはこれまでのドキュメンタリーを作ってきた経験から培われたものなのでしょうか?
私は韓国総合芸術学校の放送映像科という、韓国で数少ないドキュメンタリー制作を学べる大学にいました。ドキュメンタリーの倫理観については、インタビュー方法論という授業で学びました。インタビューはただ単に質問して答えるものではなく、関係性が重要だという内容だったと思います。
韓国ではインディーズのドキュメンタリーの歴史は浅いので、ドキュメンタリーの制作方法についてはまだ体系化されていません。今は体系化しようと努力している過程だと思います。その中で、常に論争となるのはそういった倫理的な悩みをどのように解決したらいいのか、ということなんですね。結局は現場でのケースバイケースになりますが、悩みは常につきまといます。ですから、個別のケースを考えながら改善しようと、その問題を共有して似たようなケースが発生したらどのように解決したらいいのか?韓国の作り手たちは考えて努力しているところです。韓国でも倫理的な問題はまだまだあるので、健全な状況を作らなければいけないと私は思っています。

―ありがとうございました。ここからは映画から離れて韓国での映画製作事情について伺わせてください。韓国映画界といえば、やはり大作が思い浮かびます。『記憶の戦争』のように、女性スタッフでドキュメンタリーを製作するということは、韓国映画界の中でどのような立ち位置なのでしょうか?
一言で韓国映画といっても、商業映画もあればインディーズ映画もあります。インディーズの中でもドキュメンタリーがあったり、劇映画があったりアニメがあったり様々です。この十年間で、韓国では女性監督がたくさん登場しています。監督だけでなく、女性プロデューサーや撮影監督とも作品を作ることが多くなりました。その中で、独立して自主制作をしている方もいれば、商業映画の方にいく人もいます。
やはり韓国では、商業映画で女性が活躍する機会が少ないですので、ドキュメンタリーで女性が小規模ながら少ない予算で作る方が制作しやすいという実情があります。だからドキュメンタリーの方に女性が集まる傾向がありますね。
―韓国ではドキュメンタリーの作り手はどのような生活を送っているのでしょうか?日本だとなかなか厳しい生活を送る人が多いのですが・・・
韓国でドキュメンタリーを作っている人が豊かな暮らしをしているかというと・・・やはりそうでもないですね。運のいい人はほんの一握りで、やはり芸術に携わる人は基準以下の生活を送る人が多いように感じます。
また、韓国は女性監督の活躍が目覚ましいですけども、それは映画を教える学校が存在し、そこで育った人たちが在学中に短編をつくり、そこから長編をつくって成功するネットワークが存在しているからです。また、韓国では毎年たくさんの映画祭が開催されていますので、女性の監督が作品を発表する機会が増えてきています。とはいえ、そうやって脚光をあびた女性たちがその後生き残れるかは未知数です。映画祭の参加者の50パーセントが女性であっても、そこから予算の大きい作品にたどり着くのはやはり男性なんですね。生き残って撮り続けられる女性の数は少ないです。また、映画学科に進学する女性の数はとても多いんですけど、進学はしたものの生き残らずに消えていく人も同様です。そういったことも解決しないといけないと思います。
―なぜ女性監督は生き残れないのでしょうか?
これまで成功した映画は男性的な作品が大半です。配給も制作も収益をあげないといけないので、女性より男性が主役の映画が好まれます。ですので、女性が主役で女性が監督するようなケースは稀なんです。そのために、女性が登場する映画は出資も少ないですし作られる機会も減る、とうことの繰り返しになるんですね。ドキュメンタリーも同じです。
そこで大切なのは、誰が決定権を持つ人物なのかという事です。男性が社長で決定権を持つと、どうしても男性の物語を選びがちになります。自然と男性が出てくる作品がスクリーンにかけられることになります。これからはたくさんの女性が決定権をもったり、配給会社の社長さんも女性が増えたり、女性のプロデューサーや監督がまた増えてきて、女性が作ったものもお金になるんだという成功例を見せていくのも大切だと思います。
―ありがとうございました。最後に日本のドキュメンタリーに期待することはありますか?
私自身が女性でもあるので、日本で女性がどのように作業をしているのか知りたいですね。韓国ではフェミニズムの高まりもあり女性が活躍していますが、同じ時代を生きる日本の女性たちが作った作品は映画祭などで紹介されない限りなかなか見る機会がありません。ですから彼女たちの作品を見て、交流したいと思います
。
(聞き手 李玉美・満若勇咲)

『記憶の戦争』
監督:イギル・ボラ(『きらめく拍手の音』)
プロデューサー:ソ・セロム、チョ・ソナ
撮影:クァク・ソジン
エグゼクティブプロデューサー:イギル・ボラ
プロダクションデザイナー:クァク・ソジン
編集:パトリック・ミンクス、イギル・ボラ、キム・ナリ、キム・ヒョンナム
音楽:イ・ミンフィ
製作:Whale Film |英題:UNTOLD |原題:기억의 전쟁
2018年|韓国|韓国語・ベトナム語|カラー|79分|DCP |©2018 Whale Film
宣伝美術:李潤希
配給・宣伝:スモモ、マンシーズエンターテインメント
公式サイト:_https://www.sumomo-inc.com/kiokunosensou
公式Twitter:@kioku_sensou
公式Facebook:fb.com/sumomo.movie