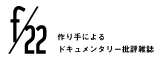劇場版『荒野に希望の灯をともす』公開記念 アフガニスタンで与えられたもの ~中村哲医師を悼む~
劇場版『荒野に希望の灯をともす』公開を記念して、f/22第3号に掲載した谷津賢二監督の記事「アフガニスタンで与えられたもの ~中村哲医師を悼む~」をこの度期間限定で公開します。
映画に合わせて是非ご一読ください。

谷津賢二(劇場版『荒野に希望の灯をともす』監督) 聞き手 江藤孝治(f/22編集委員)
二〇一九年一二月四日。長年アフガニスタンで人道支援に携わってきた医師の中村哲(当時七三歳)東部のナンガルハル州で何者かに銃撃され死亡しました。
中村哲医師のアフガニスタンでの活動を 二〇年に渡って追い続けてきた谷津氏は、何を見て、何を感じたのか。中村医師の目には日本のジャーナリズムはどう映っていたのか。 中村氏を最もよく知る、ドキュメンタリーの現場人の言葉に耳を傾けます。
※これは二〇二〇年一月二〇日に開催されたf/22第二号刊行イベントの収録です。
谷津 日本電波ニュースの谷津と申します。喋るのは苦手なのですが、中村医師の映像を記録してきた者の責務として中村医師の話、私の拙いカメラマンの話ですが聞いて頂ければと思って参りました。どうぞよろしくお願いいたします。
江藤 今、改めていかがですか?僕は中村医師の訃報を信じられない気分ではあるのですが…
谷津 そうですね・・・皆様もご承知の通り、二〇一九年の一二月四日に中村先生は亡くなりました。私も心の空白はものすごく大きいのですが、このまま黙ってアフガニスタンについてみんなが無関心になるとか、このままではいけないなと思っていまして、中村先生はきっと、怯むなといって叱咤してくれたんだろうな、と中村先生の映像を久しぶりに見て思いました。
江藤 二十年追い続けたのは、谷津さんただ一人と伺っています。なぜ追いかけることになったのでしょうか?
谷津 きっかけとしては一九九八年に中村医師が書かれた『ダラエ・ヌールへの道』という本を読んだことが始りでした。私の会社は日本電波ニュースというドキュメンタリー番組を制作する小さな会社なのですが、そこにいた企画を考える人間と、この先生はすごい、ぜひドキュメンタリーにしてみたいという話をしまして。そこでペシャワール会に連絡を取ったところ、中村先生はあまり取材を好まないので即答できない、と返答がありました。そして、まず中村先生にちょっと会って話をしてみてくれないかと打診があり、中村先生がたまたま日本に帰国しているときに三〇分くらいお時間をいただいて、お話をして取材の許可をいただいたんです。
当時、中村医師が力を入れていたのはヒンズークッシュ山脈の標高四〇〇〇メートル近い高地の無医村を医療器具、薬、食料、テントを持ち、馬に乗って巡回診療する活動でした。そこで私たちは巡回診療キャラバンについて行かせて頂いたんですね。私とディレクターの二人で一カ月ほど撮影して、NHK-BS1の日曜スペシャルという番組で五〇分のドキュメンタリーとして放送されました。これが私が初めて中村医師を撮影した経緯ですね。
江藤 中村医師は難しい方だというお話がありますが、すんなり取材できる運びになったのですか?
谷津 今となっては、先生がなぜ許可をくださったのか、ちょっと私も分からないのです。私の記憶にあるのは、東京の喫茶店で中村医師から「君は何をしたいのか」と問われて、私が「巡回診療についていきたいです」という話をしたら、幸運なことに許可を頂けたということですね。
江藤 当時は、中村医師はメディアで取り上げられていた人なんでしょうか?
谷津 私の知る限り、私の取材が最初のテレビ取材ではありません。福岡では当然前から知られていた方ですので、新聞は西日本新聞にはずいぶん取材はされていましたし、テレビもいくつかNHKとか地元福岡のテレビ局は取材をされていましたが、現地での取材は本当に数が少なくて。たとえばNHKが一度か二度取材をしたかとか。それもパキスタンがほとんどのようで、取材は少なかったようです。
江藤 過去の取材によって中村医師は取材嫌いになったと伺ってますが・・・
谷津 クルーの方々を悪く言うつもりはありませんが、私が伺っていた話だと、中村先生の取材に入った方々が、ちょっと、「貧しい子供たちの家に行ってくれませんか」とか、貧しい地帯に一緒に行って少年たちのケアをしてくれませんか、という話をされて、中村医師が、自分でもおっしゃっていましたけども、「私はドクターであってアクターではありません」と言って、その場で帰って頂きましたと当時中村医師はおっしゃっていました。
江藤 取材を途中で切り上げて?
谷津 そうだったようですね。
江藤 そのあとに谷津さんが入るわけですよね?
谷津 そうですね。当時の事を思い返すとですね、当時は九八年ですから、インターネットは存在してましたけどまだ普及はしていなくて、パキスタンと日本ではなかなか電話も通じないという状況でした。ですから、どういう取材をするのかという打ち合わせができなかったんですね。ですので、ここからここまでは取材を受け入れてくださいという話をして、パキスタンに入りました。そして数日間、中村先生と一緒にいただけで、「この先生には何もリクエストはできないな」と強く感じたんですね。それは中村医師がやっていることが医療現場であって、我々取材者があれこれでしゃばるわけにはいかない、と。中村医師の巌のような雰囲気に気圧されて、何も言えずに取材が始まりました。そして、同行した一カ月間、私たちは中村医師が行くところにただついて行くだけしかできませんでした。
江藤 まる一カ月ですか?
谷津 一カ月ですね。山での撮影と、パキスタンのペシャワールでも診療の撮影があったんですが、基本的にはこちらからは何も言いませんでした。今日はテレビ業界じゃない方もたくさんいらっしゃると思うので、すこし補足しますね。テレビのドキュメンタリー、それも十日やニ週間という限られた時間で取材させていただく場合はですね、ある程度、この場面を取材させてくださいという打ち合わせが事前にあって、そういったスケジュールの下に取材する事が多いのですね。ですが、その時の取材は全くそういうこともなく、中村医師が山に行けば山について行く、自分の病院で診察をすれば診察を撮影するするというように、ひたすら後をついて行くだけでした。
江藤 僕はディレクターですので、限られた時間や予算の中で、番組を構成できる撮れ高を優先する状況で現場に入ることがとても多い立場です。本来であれば、先ほど谷津さんが仰られた取材方法がスタンダードであるべきものだとは思うんですが、なかなかそうはいかないですね。取材中にこのままで番組が成立するのか?という焦りなどはありませんでしたか?
谷津 もちろん「これで番組ができるのか」というような、自分の職業人としての焦りはありました。ですが、それ以上に中村医師が持っている人間的な魅力、それと現地で山の民に対して中村医師が示す親愛の情とかですね、それに対する山の民からの中村先生に対する尊敬と、親愛の情のやり取りそういう関係を見てしまうと、これは気恥ずかしい言い方ですけども、撮れ高とかいい映像が撮れたかとかあまり気にならなくなってしまったんですね。最初の取材の時から私は中村医師の虜になってしまって。この先生のことをもっとずっと撮ってみたい、取材をしてみたいという気持ちは、この最初の取材の時に芽生えたんです。
これは人づてに聞いたんですが、もともとメディアが好きではない中村医師が、なぜ私どもの取材をまあ二一年間も受け入れてくれたかというと、中村先生は「電波ニュースの人間は何にも言わんとー」って言ったらしいです。何も言わないからいいというのは、私達の業界では実は難しいところでして。先程も申し上げましたが、取材者から取材対象者への働きかけや事前の綿密な打ち合わせが基本なんですね。それがないまま取材を行ったというのは、普通ではないやり方で取材が始まったと言えると思います。その後二〇一九年の四月に行ったアフガンでの取材が、最後の現地取材になりました。普通ではない取材方法だったからこそ、今年まで二一年間取材をさせていただけたことにつながったと私は思っています。
江藤 なるほど。同じ業界人として非常に深いものを感じますね。一方で、放送された番組に対してプロデューサーから厳しい感想を頂いたと伺っています。
谷津 はい二〇〇一年にNHKのETV特集で『戦乱と干ばつの大地から』という番組を作り放送しました。その時にこんな経験がありました。放送終了後担当プロデューサーからこんな話をされました。「NHKのかなりのポジションにいる方が番組を見てくださり、良い番組だったけれども取材対象者と取材者が切り合って撮ってきたようには見えなかった」と言われたんですね。
そのとき私が思ったのは、確かにドキュメンタリー撮影の戦術的な一つのやり方として、ある人の人物像を浮かび上がらせるために、その人が話したくない、あまり見てもらいたくないところも、力業で話を聞き出すとかですね、その人の生き様を切り取ってくるというやり方があるんです。ですが私は最初から中村哲医師にはそれが通用しないと思ってしまったんですね。通用しないと思ってしまうこと自体、私は取材者として失格かもしれません。ですが、五年十年と取材を重ねていくうちに、自分と中村医師の関係が取材者と取材対象者という関係が溶けてしまってですね、実は中村医師の映像記録をする係だと言うような意識で二一年間撮っていたんです。
それに対して中村医師はどう思っていたのかきちんと聞いた事は無いんです。ですが、昨年二〇一九年四月の最後のアフガニスタン取材時に中村医師から「谷津さんはジャーナリストじゃなかもんね」と言われたのです。これは自分としてはどう受け止めていいのか判断に迷いました。もちろん中村医師はジャーナリズムの意義にリスペクトがある方なんですが「取材に行って書いて発表して、はい終わり、と言うことでは本来なかろう」という思いを常に持っていて、よく「どんなことでも一つのことを長く続けると言う事はとても大切だ」とおっしゃっていたんです。そしてもう一つ感じたことは、取材者と取材対象者の垣根を超えてしまうことでできる新たな関係があったのかもしれません。当然その関係性は良し悪しを包含していて、仮に中村医師が不正を働くなどということがあっても、そうしたことに踏み込めなくなる可能性があります。一方で、その関係性故に見せてくれる表情や心情もありました。
さきほどお話した「一つのことに専心する」その考えに基づいて、中村医師は三五年間アフガニスタンとパキスタンの二カ国という限定された世界で苦境にある人々に寄り添い続けて来たのだと思います。私はその中村医師の深い思索に支えられた活動に驚き、心動かされ、その後、何度も取材をお願いすることになりました。だから中村医師は取材をし続ける私に対して、ジャーナリストではなくある意味、同志的な目線で好ましく思ってくださったのかなと思います。
江藤 中村医師は撮られると言う事は本質的に嫌ではなかった、やっぱり伝えたい何かがあるのですね。
谷津 中村医師が絶対に撮影が嫌だと言うわけではないと思います。私が人づてに聞いたエピソードを紹介しますね。二〇〇〇年に中央アジアで大干ばつが始まって、子供が次々と死ぬ、お年寄りもどんどん弱っていく状況に陥ったんですね。その時、中村医師たちはインターネットを使って日本語で「パキスタン アフガニスタン 干ばつ」と調べてみたんですが全然ヒットしなかったらしいんです。試しに英語で「drought Afghanistan」とか「Central Asia」と入れたところ数万件がヒットしたと。世界的には中央アジアの干ばつと言うのは大問題になり始めていたらしいんですね。その最中、現地にいた中村医師としてはペシャワール会を通じて、この惨状をとにかく伝えたいと。テレビ局、新聞社にプレスリリースと言う形で出しました。そのときに、中村医師に応えて現場に行ったのは私ども日本電波ニュースだけでした。それが二回めの中村医師の取材になりました。電波ニュースは社員が二二人しかいない小さな会社なのですが、中村医師は「干ばつ被害を熱心に訴えても応えてくれたのは、小さな映像制作会社だけだった」と書いていました。
やはり中村医師は撮られると言う事は本質的には好きじゃないんだと思います。ですが、干ばつ被害は長く取材しないとなかなかわからないですので、ピンポイントで起きている事を伝えるよりも長く取材して映像を出すということの意味は理解して下さっていたと思います。