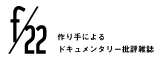続報『童貞。をプロデュース』問題 当事者同士の対談ーそこから見えてきたもの(5)
ドキュメンタリーの作り手の立場から、対談に参加して
f/22編集委員 川上拓也
加賀氏が受けた三重の被害
まず、加賀氏が『童貞。をプロデュース』との関わりの中で受けた被害について、大きく三つに分けて、改めて確認しておきたい。ドキュメンタリーの作り手として、自分の仕事が持つ加害性について考えるとき、加賀氏が受けた被害の実相をもう一度捉え直しておくことには、意義があるはずだ。
一つ目は、制作時、撮影時の被害である。
問題のシーンの撮影時において加賀氏が受けた、同調圧力の空気の中でのパラハラと性行為の強要(また羽交い締めという直接的暴力)や、望まないセリフ(「AV女優が綺麗なものとは思えない」)や演出(コイントスや告白のシーン)を「受け入れさせられた」パワハラがそれに当たる。この被害については、その現場全てに関わった松江氏も自らの加害を認め、問題のシーンに関与したカンパニー松尾氏も加害を認めたことになる。両者に共通していたのは、当時はそれが「加害行為」であるとの認識が、全くなかったことだった。
——————–
二つ目は、望まない上映を十年に渡って続けられたことによる被害である。
加賀氏はもともと共同制作者の立場で本作に参加したが、編集権はなかった。問題のシーンについては編集完了の時点で内容を確認し、シーンの使用を明確に拒否している。しかし、松江氏に押し切られる形で、ガンダーラ映画祭のみでの作品上映に同意していた(この同意も、松江氏との力関係が不均衡な状態の下に、取り付けられたことは忘れてはならない)。
その後、直井氏が配給の立場で参加し、劇場公開が決まっていく過程においても、一年目の劇場公開中も、その後2017年まで十年に渡って毎年続けられた記念上映においても、上映を望まない加賀氏の姿勢に変わりはなかった。
DVD化の話が出た際の松江氏、直井氏、梅澤氏による話し合い(松江氏が「こいつ殴ってもいいですか?」と言った時)や、中野のタコス屋での直井氏との話し合いにおいても、加賀氏の訴えは軽視、あるいは無視されたと言ってよいだろう。
その後、二年目の上映前の段階でも、着信拒否をされていた加賀氏が友人の携帯で松江氏に電話し、上映拒否の姿勢を明確に示しているが、松江氏はこの際も聞く耳を持たず、その訴えを無視している。(https://youtu.be/yrh-E6KQbPM)。
再三にわたる加賀氏の上映拒否の意見を、松江氏、直井氏は共に(本人たちの言葉を借りれば、「無自覚に」)受け入れないままに、十年間に渡り作品の上映を続けた。撮影時の被害に加え、この「望まない上映の継続」によって受けた加賀氏の被害は重い。
本作品が「ドキュメンタリー」として公開され続け、作品の虚構の「ストーリー」や加賀氏の望まなかった「セリフ」が、本人の「実像」と結び付けられたままに観客に届けられ続けたことによる被害の重さについても、改めて指摘したい。
直井氏は、当時、本作を「ドキュメンタリー」として公開することの重大性への認識がそれほどなかった(「楽観視していた」)と述べていたが、日本映画学校(現:日本映画大学)でドキュメンタリー制作を学び、本作公開の七年前には、自身のセルフドキュメンタリー『あんにょんキムチ』で、すでに一定の評価を受け、「ドキュメンタリー監督」を名乗っていた松江氏が、本作を「ドキュメンタリー」と銘打って(事実、公開時のチラシには「愛と勇気と感動のドキュメンタリー」との紹介文が載せられている。)公開を続けていくことの「恐ろしさ」への自覚が全くなかったとすれば、ドキュメンタリーの作り手としての基本的な、被写体への、また観客への責任感があまりに薄かったと言わざるを得ない。
——————–
三つ目は、2017年の舞台挨拶後の共同声明文による被害である。
今回の対談で、この声明文は「作品を守るため」の欺瞞的表現や、誤った認識(もしくは虚偽と言うべきかもしれない)による記載が、至る所に存在することが明らかになった。端的に、この声明は加賀氏の告発や主張が嘘であるとの前提で書かれているため、この文章が撤回・訂正され、そのことが社会に広く周知されるまで、加賀氏は名誉毀損の被害を受け続けることになる。
2019年に出された謝罪についても、松江氏は声明自体には触れておらず、直井氏も2017年の声明のどの部分が具体的に「事実と異なる内容」であったのかを明確にしていなかったため、不十分な謝罪であったと言わざるを得ない。
また、性暴力被害の観点からも、加害者側が加害行為がなかったと公に表明し、二年以上その立場を維持したことは、重大かつ継続的な二次加害と言えるだろう。
この声明については、今回の対談を通し、両者共に撤回と訂正、その周知の努力を続けることを加賀氏に約束した。
上記三つの被害に加え、松江氏が加賀氏への誹謗中傷を行なっていたことも明らかになっている(「当たり屋で生計を立てている」「頭がおかしくなった」など)。この事により加賀氏が受けた被害については、現在においても、加賀氏が直接認識していない範囲にまで広がっている可能性があることを、再度確認しておきたい。
三者に共通する加害意識の薄さ
本対談に参加した第三者として、最後の松江氏の取材を終えて最も強く残った印象は、加害側である三者に共通した、加害意識の薄さである。
カンパニー松尾氏は、最初にこの問題における自身の加害性を認識したのは、2017年の舞台挨拶での事件を知った際だと述べた。実際に性行為の強要に加担した撮影現場、またその後も、自らの加害行為への認識はなかった。
松江氏は問題のシーンの撮影時から、直井氏は劇場公開時から、加賀氏の訴えを何度も直接聞いていたが、その訴えを軽視または無視していた。両者が2017年の舞台挨拶後に出した声明の内容を考えると、また、その後、加賀氏の話し合いの条件(公開前提)を飲んででも謝罪する態度を、今回の対談まで積極的に示さなかったことを考えると、自分たちの加害行為の「重さ」を本当に認識し始めたのは、藤本氏や本誌のインタビュー記事を読んでから、つい最近だということになる。これは筆者の印象になるが、今回の対談を通してようやく認識した部分も、少なくなかったように思われる。
この認識の薄さに、対談に同席して改めて驚いたと同時に、「性暴力やパワハラの加害者には認知の歪みがあり、加害自体の認識を持てないことが多い」という、一般的に言われる加害者心理が、被害者をどれだけ追いつめるのかを再確認した。
もし撮影時に、上映時に、舞台挨拶の事件の瞬間に、自らの加害意識を誰かが重く持てていれば、加賀氏の十二年に渡る被害はなかったかもしれない、もっと浅かったかもしれないと思うと、やりきれない思いになる。
「加害者の加害意識の薄さ」についてドキュメンタリーの作り手として思うことは、もし自分が撮影現場や編集や上映過程において、何らかのハラスメントの加害者になったとして、その時、自らの加害性を「認識できない」かもしれないという恐ろしさだ。
加賀氏は明確に拒否の姿勢を示していたにも関わらず、松江氏は自らの加害性に気がつかなかった。私たちが日常的に撮影現場で撮らせていただく方達は、そこまで明確に拒否の姿勢を示さないかもしれない。その状況でも、本当に現場で自らの加害性に気がつくことが出来るのだろうか。
この危険性を回避するために、現場にも、ポスプロにも、上映においても、制作プロセスや作品自体に対しての「複眼性」を持たせること、つまりは監督以外の立場で作品に関わる人間がおり(つまりはスタッフだ)、各々の倫理観と主体性を持って、監督と「対等の立場」で話し合ったり、相談したりできる状況を作ることは、一つの対策にはなるかもしれない。
本件では、松江氏が監督・編集を担当しており、加賀氏は出演者と撮影を兼ねていたと言えるが、通常言う「撮影スタッフ(カメラマン)」としては扱われていなかった。また、松江氏と加賀氏の関係性は「対等の立場」ではなかった。現場の倫理に対する「複眼性」はなかったと言えるだろう。
もし自分が「三人目」のスタッフとして、録音の立場で問題のシーンの現場にいたら、編集マンとして参加していたらと考えてしまうと同時に、参加していたとしても、その当時(性暴力被害やパワハラについてのリテラシーは、現在と比べて低かっただろう)、はっきりと松江氏の「演出」にNOと言えていただろうかと自問してしまう。
さらに述べておきたいのは、たとえ現場での複眼性が担保されていたとしても、監督とスタッフ全員が、自分たちの撮影行為によって被写体の方を「抑圧」している可能性は常にあり、全員がそれに現場で気がつかない可能性もあるという点だ。ここにドキュメンタリー制作の本当の恐ろしさがあると思う。
例えば、監督・撮影・録音の三人が撮影現場に入った時、被写体の方が、そのロケに「いくらかかっているのだろう(交通費・宿泊費・スタッフのギャラなど)」と思うことは珍しくないはずだ。そのような認識の下に、「仕事に来た」三人を前にして、本当は嫌だと感じている内容の撮影にも、「安くないお金もかかっているし」「これで撮影を断るのも申し訳ない」と、愛想笑いをして「大丈夫です」と「同意」してしまうことは十分に考えられる。その時、その「愛想笑い」によって示された「拒否感」の深刻さを現場で正確に判断し、「自分たちの撮影行為が持つ加害性の認識」へと即座に変換し、それを「撮らない」という行動に移すことが出来るだろうか。また、「ドキュメンタリー作品として劇場公開すること」への理解が、被写体の方の中にどれほど正確にあるかという点についても、やはり作り手側が細心の注意を持って、配慮する必要がある。 私たち作り手には、常に、被写体となっている方達の「同意」を、あくまで一時的なものとして捉え、編集時、劇場公開時、その後の上映会が続いていく中においても、都度、その同意の「真意」や「変化」について、被写体の方達との関係性を維持する中で、何度でも確認し続ける責任がある。そして、その責任の一端は、宣伝・配給・劇場に関わって仕事をしている人たちの中にも、全くないとは言い切れないだろう。制作者たち自身(監督・スタッフ)が気がつかない部分で倫理的な問題があった場合、作品が観客に公開される前の段階で、その問題に最後に気がつく可能性を持っているのは、宣伝・配給・劇場に関わるスタッフたちである。作品を作り公開する仕事に携わる誰もが、自らが日々の業務において「凡庸な悪」として振舞ってしまう危険性を自覚する必要がある。
当事者間の問題ではなく、社会全体の問題
加賀氏は制作時、一年目の劇場公開時から、松江氏と直井氏に自らの思いを何度も伝えており、本作公開の二年目が始まる前の段階で(前記のyoutube動画を参照されたい)、すでに松江氏、直井氏との直接の対話が困難な状況に追い込まれていた。「当事者間での話し合いでは解決が望めない」「自分の言葉では伝わらない」状態がさらに継続した後の2017年に、あの舞台挨拶での事件が起こった。
この経緯を踏まえれば、加賀氏が舞台挨拶で起こした「事件」は、松江氏や直井氏に自分の被害を認識させるための「最後の強行手段」であったと同時に、当事者ではない、外部の「社会」に対してのSOSの意味を持っていたことも明らかだ。共同声明の後においても、加賀氏が一貫して「公開前提での対話」を求めていたのは、加賀氏の立場を想像すれば当然の要請だったと言えるだろう。
また、より一般に言っても、性暴力被害を訴えている被害者に、加害者との対話による解決を期待することは暴力的である。カンパニー松尾氏との対談の際にも述べたが、もし被害者が女性で、望まない口淫をされることを強要され、その現場を撮影され、同意なしに劇場公開されたとして、その現場を作り(演出し)、作品を完成し、公開した監督と、「当事者同士で話し合え」と言えるだろうか。この態度には「男性被害者」への隠された偏見や、無意識の差別という、社会側、つまり「第三者」側にある状況も関わってくるはずだ。
上記の文脈から、本件を「当事者間の問題」として、当事者同士の解決を求めたり、待ったりするのは、端的に、文脈の無理解による不適切な態度と言えるだろう。しかし、舞台挨拶の事件が広く認知された時においても、そのような態度を示す「関係者」や「第三者」は多かった。このことは、残念ながら私たちの社会には現在においても、性暴力被害者、男性被害者が置かれる状況についての理解が足りていないことを示しているだろう。
また、仮に「ドキュメンタリー業界」というものがあるとして、本件に対する反応が、舞台挨拶後、ほとんどと言っていいほど出てこなかったことも、業界の中で仕事をしている身として、改めて指摘しておきたい。
私の知る限り、この件に関してSNSや個人のブログなどを除いた媒体において、いわゆる「ドキュメンタリー業界」の中で正式に出された文章は、2017年の山形国際ドキュメンタリー映画祭にて、映画祭の期間中に毎日発行され、観客に無料で配られる「デイリー・ニュース」に、マーク・ノーネス氏が書かれた「カメラの「牙」を見つめてー佐藤真の地平線のないドキュメンタリー倫理」という短い文章と、たった一年前に創刊し、残念ながら一般の知名度もまだまだ低い本誌『f/22』の文章だけであった(全ての媒体を筆者がチェックできている訳ではないので、もし他にあったとしたらお詫びしたい)。SNSを含めたとしても、舞台挨拶後、2019年12月の藤本氏の記事の公開と、その後の謝罪文が出される前までにおいて、この件について積極的に発言している「ドキュメンタリー業界」の人間は、数えられるほどしかいなかったと思う(最近になり、ヤン・ヨンヒ氏や想田和弘氏は自身のtwitter上で本件に対する見解を示した)。
「作品を見ていないから」コメントできない(もしくは、するべきではない)という姿勢もSNS上では多く見受けられたが、加賀氏自身も述べていたように、性暴力被害の映像を「見る」こと自体が、被害者へ更なる苦痛を与えることへの認識と配慮が足りないのではないだろうか。
加賀氏は明確に、本作を基本的には「見て欲しくない」と述べた。被害者が誰にも見て欲しくないと思っている映像を、単に「見る」ことが持つ加害性についても、私たちはもっと認識すべきだろう。そして、本件の加害と被害の重大性は、たとえ「作品」を見ていなくとも、その経緯や加賀氏の発言を追えば、十分に理解できたはずだ。
伊藤詩織氏の事件とその後の流れについては、本件と異なり、様々なドキュメンタリー関係者が自らの意見を述べてきている。彼女が山口敬之氏から加害行為を受けている映像を見ていないことを理由に、彼女を被害者として認識し、自らの見解や認識を示すことを躊躇するだろうか。彼女の被害告発の「真実性」を、様々な文章や映像を通して私たちは判断している。「不完全情報系」の中で意見を発することしか出来ないのが、私たちが常々置かれている現代のメディア環境であるなら、本件においても同様に、「作品を見ていないから」コメント出来ないという態度に妥当性は認められないし、その態度は「映画作品批評」に求められるモラルと、「社会的事件」に対する批評におけるモラルの、履き違えによるものではないだろうか。
本件に対する反応について、最後に触れておきたいのが、ドキュメンタリー番組やドキュメンタリー映画の制作会社である、ドキュメンタリー・ジャパンが中心となって毎年開催している、「座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル」の対応だ。このフェスティバルには、2017年の舞台挨拶時の事件と共同声明が出た後の、2018年、続く2019年でも、フェスティバルとして特に本件についての見解表明や言及はないまま、松江氏が上映作のゲスト・セレクター、またトークゲストとして参加している。この件について、ドキュメンタリーの作り手、またフェスティバル開催者として、特に何も語る立場にはない、その必要はないとの認識があったのかどうかは分からないが、少なくとも筆者個人としては、疑問の残る対応であった。社会的に「発言力」のある、「権威」のある(フリーランスの一スタッフの筆者の立場から見ると、ドキュメンタリー・ジャパンは業界の「権威」の一つである)ドキュメンタリーの作り手の立場として、本件について何らかの見解を表明して欲しかったというのが、一個人として『f/22』へ参加する前から、本件について公開SNSで本名で発言を続け、その後、本誌コラム上で発信しても、社会への影響力が皆無であった筆者の隠さぬ本音だ。
このような反応の「鈍さ」が、果たして上記で述べたような文脈の無理解や認識の甘さが原因なのか、狭い業界内で波風を立てたくないという日和見主義からなのか、松江氏とも「色々一緒にやってきた」立場としての「仁義」からなのか、内部的な他の理由からなのかは私の立場からは知り得ないが、少なくとも観客の立場から見たときに、自浄作用が全くない「業界」だと言われても、反論はできないのが現状だろう。
加賀氏が対談において三者に求めたように、「仁義」よりも「社会的な意義や公共性」を重視して取る発言や行動が、現状の社会をより良い方向に動かしていくために、私たち一人一人が持てる「責任」ではないだろうか。
ドキュメンタリーを作ることを生業としている筆者としては、自らの仕事が持つ加害性を自覚するからこそ、本件について口を噤むのではなく、考え続け、公に発言し続ける責任があると考える。
本当に「十二年前」の問題なのか
問題のシーンについては、三者ともに、「今の認識ではありえない」という趣旨の意見を語った。しかし、本当にそうなのかと改めて考え直す必要があるのではないか。AV強要問題についての様々な告発を今も見ていれば、このような「抑圧/被抑圧」という関係性の中で発生する様々なハラスメントは、「現在はない」などとは言えないだろう。筆者の個人的な実感としても、映画業界において、同様の様々なハラスメントは、今現在でも至る所に存在していると言わざるを得ない。例えば、アイドルを目指す少女たちと、アイドルをプロデュースする立場にいる人間との、圧倒的に不均衡なパワーバランスの中で、パワハラ的な面接や指導が行われていないとは、誰にも言えないのではないだろうか。そのような場面を撮影し、作品化し、劇場公開している作品例も、近年においても存在しているのではないか。それを「少女たちの青春ストーリー」としてエンタメ化し、パワハラの実状を「ノリ」で笑いにして消費する空気も、現在においても存在しているのではないだろうか。そこに映される被写体の少女たちに、「本当は心底嫌だったが、被害の重さへの自己認識から逃れるため、自らの中でも、笑いのフィルターを通して被害を軽く扱おうとしていた部分がある」という、十二年前の加賀氏の心境を重ねてしまうのは、私だけだろうか。性暴力の文脈では、被害者の方達が、自らの被害を被害として正確に認識するまでにも、否認や忘却のプロセスを経て、長い年月を要することが指摘されている。その時はなかったとされた被害でも、実際になかったとは言えない状況が存在する。
対談の中で、加賀氏がしきりに強調していた「この話は自分たちの問題だけではない」という切実な主張が、当事者だけではなく、第三者としての私たちにも、現在進行形で突きつけられていることを忘れてはならない。
最後に
今回の対談では、加賀氏に対し、カンパニー松尾氏、直井氏、松江氏が、それぞれの立場から、自らが関わった加害行為について認め、謝罪があった。この問題の解決への「最初の一歩」として、このような対談が実現したことについては喜びたいと同時に、十二年間に渡る加賀氏の被害への、作り手側・見せ手側の今後の「責任」の取り方は、一度の謝罪だけで終わるものではないことを改めて確認したい。また、同じ「ドキュメンタリーの作り手」として、三者を糾弾する立ち位置ではなく、被害者の告発を「いつでも受ける可能性がある立場」として、あくまで「潜在的な加害側」としての立ち位置で、本件を真摯に捉え続けたい。 本件の今後の動向については具体的に決まっていない部分が多いが、本誌としては継続した取材を進めていくと共に、この問題について知った誰もが、より「第三者としての当事者性」を持ち、様々なハラスメントや性暴力を認めない社会を目指して、また映画製作における(更にはより一般の生活・労働環境における)「抑圧/被抑圧」の構造からの脱却を目指して、より広く深く、社会全体での議論が進むことを望みたい。
※本記事は2020年1月14日(1月21日の松江氏、直井氏の新たな謝罪声明が公開される以前)に執筆を終えた段階での内容を、そのまま掲載している。